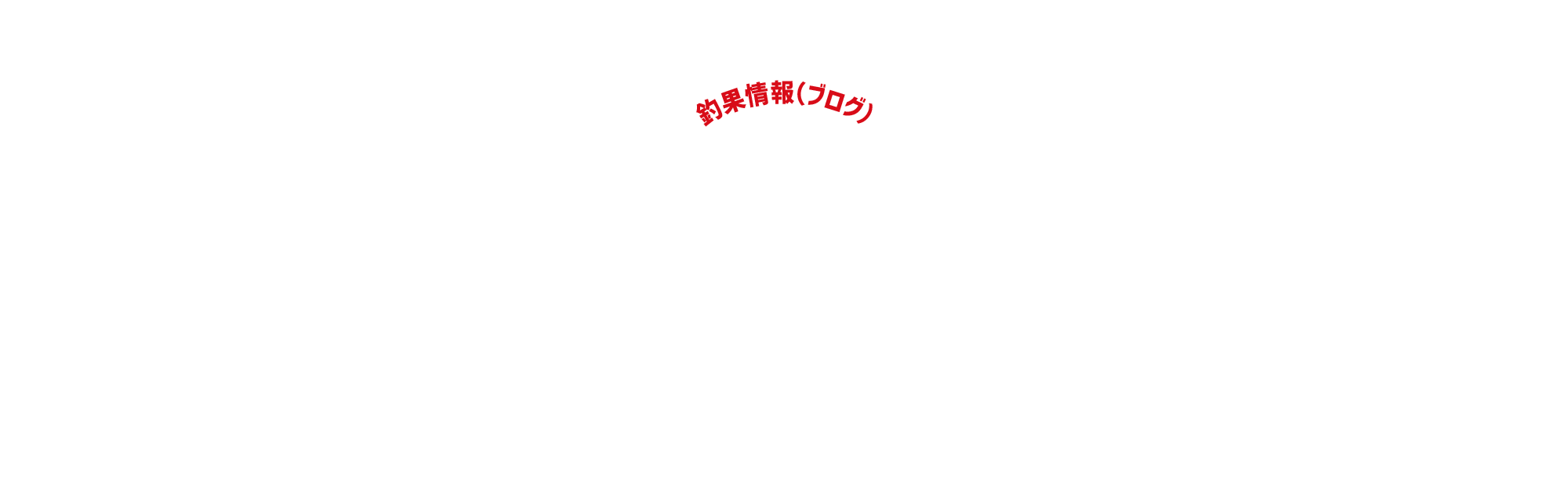皆さんこんにちは!
正福丸、更新担当の中西です。
さて今回は
~“海に出る前に、陸で整える”~
遊漁船(チャーターボートや釣り船)は、海に出るたびに塩・風・波・日射といった自然の影響を全身で受けています。
見た目はピカピカでも、内部は確実に消耗しているのが現実です。
そのため、遊漁船のメンテナンスは「壊れてから直す」ではなく、「壊れないように整える」“予防整備”の思想が何よりも重要です。⚙️
🛥️ 1. 海水がもたらす最大の敵「塩害」
海上で最も厄介なのが塩分による腐食。
エンジン、配線、金属部品、電装機器…あらゆる箇所に塩が入り込み、微細な腐食を進行させます。
特に以下の部位は要注意です。
これを防ぐ基本は「真水洗浄」です。
航行後、船体全体をホースで洗い流すだけでなく、エンジン冷却経路の真水循環、デッキ下の排水確認まで行いましょう。
🔋 2. 電装系統は“塩”と“湿気”で壊れる
夜釣りや照明付き設備を多く持つ遊漁船では、電装トラブルが最も多い。
特にバッテリー端子の緑青(錆)は要注意。
見落とすと、ある日突然「エンジン始動しない」「魚探が落ちる」といった事態に。
定期点検ポイント👇
-
端子の締付けトルク
-
配線被膜の割れ・断線
-
予備ヒューズ・リレーの交換周期
-
ソーラーチャージャーや発電機の電圧安定性
また、夜釣りライト・油圧ポンプなどの高負荷装置を多用する場合は、容量に余裕のある電源設計を見直すことが事故防止につながります。
⚙️ 3. 船底塗装と防汚管理
遊漁船の燃費・速度・安全性を左右するのが船底。
フジツボや海藻が付着すると、水の抵抗が増し、燃費が悪化するだけでなく、過熱や振動の原因にもなります。
**船底塗料(防汚塗料)**は、海域・使用頻度・係留期間によって選定が異なります。
年1〜2回のドック上架が理想です。
この際、プロペラ・シャフト・アノードの消耗も確認し、腐食の進行を早めに止めましょう。
🧭 4. 年間メンテナンススケジュールの考え方
| 項目 |
点検時期 |
内容 |
| エンジンオイル/フィルター |
100時間 or 半年 |
品番指定・廃油処理含む |
| 船底塗装 |
年1〜2回 |
上架清掃・塗り替え |
| 電装・配線 |
年1回 |
抵抗測定・端子交換 |
| バッテリー |
年1回 |
電圧・液量チェック |
| 船検対応整備 |
随時 |
消火器・航海灯・救命具点検 |
遊漁船は「営業船舶」でもあるため、安全管理記録を残すことが信頼維持に直結します。
🚤 5. メンテナンスは信頼と集客を生む
釣り客が感じる安心感の多くは「整備された船」から生まれます。
ハンドルの遊びが少ない、エンジン音が静か、デッキが清潔――。
それらすべてが「また乗りたい船」につながる。
メンテナンスとは“安全のため”であると同時に、“ブランド維持”のための投資でもあります。